top of page
Karasawa Megumi
-Human Activity and Art-
Blog
copyright 2022 Karasawa Megumi all rights reserves .
検索


グループ展に行ってきました。
「ひび割れ展」というグループ展に行って来ました。完璧ではない、一見「欠点」に見えるものが、最も深い美しさを生み出す。今日のブログは、そんな大切な気づきについて書きました。

Megumi Karasawa
8月30日読了時間: 3分


タイトルひとつで、意識が変わる
作品にタイトルを付ける意味。
それは、単なる説明のためではありません。
私は「タイトルひとつで、人の意識が変わること」を信じています。
タイトルに込めた私の考えと、美術史から見たタイトルの変遷について書きました。

Megumi Karasawa
8月29日読了時間: 3分


「花時計」の予言:過去のブログが導いた個展のテーマ「まなざしと差異」
個展の開催まであと2ヶ月。ついに、テーマを発表します。
きっかけは、今年1月に書いたあるブログ記事。そこで考察した「まなざしと差異」という言葉が、今回の個展のテーマになりました。
木下佳通代さんの作品から着想を得た「花時計」の予言。葛藤の末に辿り着いた、私の創作の現在地について綴っています。ぜひご覧ください。

Megumi Karasawa
8月5日読了時間: 2分
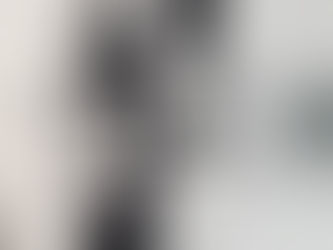

「線」の心臓:情動が宿る、具象と抽象の境界
風景からポートレートへ、そして「線」への回帰。
24年ぶりのデッサン会で、私が再認識したのは「線」が持つ奥深い力でした。それは単なる輪郭ではなく、人の内面や感情、そして見えない「構造」を描き出す媒体だったのです。
曖昧さと明確さの間で揺れ動きながら現代アーティストMegumi Karasawaの今を是非ご一読ください。

Megumi Karasawa
8月1日読了時間: 3分


デッサン会のメモから:「場」の力学とまなざしの交差
24年ぶりに参加したデッサン会。モデルさんを描くはずが、なぜか「描く人」に視線が向いた理由。そして、線とまなざしが持つ意味とは?
私の現在地を、綴りました。

Megumi Karasawa
7月31日読了時間: 3分


24年振り!?:予期せぬヒントをくれたデッサン会
24年ぶりに参加したデッサン会で、まさかの「予期せぬヒント」をもらいました。
描写力を磨くはずが、感じたのは「見る」ことへの強いこだわりでした。
この体験が、私の創作をどこへ導くのか。ぜひ読んでみてください。

Megumi Karasawa
7月30日読了時間: 4分


「空白」の先に:モノクローム絵画が暴く「見えない暴力性」の構造
風景を描く私が女性のヌードを描き、肌の色に潜む無意識の偏見に気づいた時、アートの「見えない暴力性」の構造が見えてきました。黒と白、そしてその間の「グレーの幅」が語る、普遍的な真実とは?
この個人的な探求が、あなた自身の「見えない規範」を問い直すきっかけになれば嬉しいです。

Megumi Karasawa
7月29日読了時間: 6分


風景を描く私が、女性のヌードを描いた理由
普段、風景を描く私が、今回女性のヌードを描いたのはなぜか?
作品に潜む「暴力性」というテーマと向き合う中で、私はある重要な葛藤に直面しました。それは、作家自身の表現欲求と、鑑賞者の心への配慮という、二つの相反する視点です。
この個人的な探求が、私の創作を新たなステージへと導くのでしょうか?

Megumi Karasawa
7月28日読了時間: 5分


作品は、誰のためのもの?:あるアーティストの内省と、キュレーションという応え
アート活動を持続させるには、キュレーションとセルフプロデュースのどちらを優先すべきでしょうか?
私はこの問いと向き合う中で、まず「内面」の充実に焦点を当てることの大切さに気づきました。作品の本質を深める「キュレーション」が、活動の揺るぎない核となる理由をブログに綴っています。

Megumi Karasawa
7月27日読了時間: 3分


アートは、なぜ「作って終わり」ではなくなったのか:時代が変えた作家の役割
「作品を作ることがアーティストの仕事」—その考えは、なぜ時代とともに変わったのか?
私自身、プロデュース活動が苦手で悩んできましたが、その葛藤の先に「キュレーション」という大切な答えを見つけました。それは、作品世界を深く探求するための、内向きで創造的な活動でした。
「外側」の活動ではなく「内側」の充実に焦点を当てることを選びます。

Megumi Karasawa
7月26日読了時間: 4分


展示空間を「編集」する:アーティスト主導型キュレーションの可能性
「アーティストは作品を作るだけ」という従来の考えを越えて、なぜ今、私たち自身がキュレーターになるべきなのか?
過去の作品との対話から、個展という空間を「編集」する試み。それは、作品の本質を深め、アーティストとしての可能性を拓く、挑戦的なプロセスです。

Megumi Karasawa
7月25日読了時間: 3分


筆と身体、そして知:具象表現の実践が導く、現代アートの深化
「筆と身体、そして知」。今回の展覧会で実践したポートレート制作が、私の具象表現、そして現代アート全体に新たな深みをもたらしてくれました。
作品を「描く」という行為が、いかに身体的で、いかに思考を要するプロセスなのか。その実践から見出した気づきを綴っています。

Megumi Karasawa
7月24日読了時間: 4分


展覧会を終えて:量から質へ、露出における「選択」の重要性
グループ展を終えて。
作品露出における「選択の質」の重要性。単に多く見せるだけでなく、どこで、どう見せるか。この「質」が、本当に届けるために不可欠だと肌で感じています。
この気づきが、これからの私の活動の新たな指針となります。ぜひブログで詳細を読んでみてください。

Megumi Karasawa
7月22日読了時間: 3分


『ロスト・ペインティング』探求録:六日目、閉幕。アートの新たな地平
グループ展『第9回 菜々燦会展』、無事に閉幕しました!
この6日間で得た「いい負荷」は、創作の「設計図」に。悔しさも反抗心も、心理学で言う「昇華」を経て、私のアートの「栄養源」となりました。
次なる「個展」へ。この展覧会が私に何をもたらしたか、ブログでぜひご覧ください。

Megumi Karasawa
7月21日読了時間: 5分


『ロスト・ペインティング』探求録:五日目、会場で描くポートレート ― 眼差しの歴史と新たな対話
グループ展5日目。これまで逡巡してきた「ポートレートを描く」という挑戦を、会場で始めました。
それは単なる似顔絵ではなく、絵画における「眼差しの歴史」を私なりに体験し、一期一会の「対話」を生み出す試み。作品の「再構築」と同じように、目の前の人の「存在」を捉えようとしています。
ぜひブログで、その新たな挑戦の裏側を読んでみてください。

Megumi Karasawa
7月20日読了時間: 3分


ジョアン・ミロの「焼かれたカンヴァス」から学ぶ:「深追いしない」という能動的な創造
ミロの晩年作から見えた、技術を超えた「作家の精神性」。
現代アートが求める「速さ」に背を向け、わたしが探求するのは、「深追いしない」という能動的な創造哲学です。
「待てない焦り」から生まれた「積極的な諦め」が、アーティストの成熟と作品の奥行きにどう繋がるのか。

Megumi Karasawa
7月8日読了時間: 4分


描く手を「止める」勇気:「待つ」ことが開く、アーティストの「非世間的な時間軸」
「描く手を止めると不安になる」そんな経験、ありませんか?
20代で出会ったベケットと鉛筆画が教えてくれた、私の「非世間的な時間軸」。
作品を「熟成」「発酵」させる、人間だけの特別な「待つ」時間とは?
実は、その「待てない焦り」こそ、
AIには成し得ない、物質と時間、そして人間が織りなす「仕事」の奥深さなのかもしれません。

Megumi Karasawa
7月7日読了時間: 3分


「速さ」の向こう側へ:私の創作と向き合う「非世間的な時間軸」—ゴドーが教えてくれた「待つ」アート
人間ならではの創作の「質」を問い直し、私が出会ったのは「待つ」という、意外な創造の鍵。
「ゴドーを待ちながら」が示唆する「何もしないこと」の奥深さ、そして素材そのものが為す「熟成」のアートとは。
AIがすべてを加速する時代に、芸術が私たちに求める真の価値とは何か?

Megumi Karasawa
7月6日読了時間: 7分


【作品にかける時間】「火事場の底力」と創造性:画家たちの選択が示すもの
一枚の絵に、どれだけ時間をかけますか?
私のこの問いから、人間誰もが持つ「火事場の底力」の可能性に行き着きました。
極限の集中力が創造性を爆発させるメカニズム、そして画家たちの選択の物語。
ブログでじっくり深掘りしたので、ぜひ読んでみてください!

Megumi Karasawa
7月6日読了時間: 8分


アーティストの問い:不均衡な現実に挑む『準備された即興性』
「描いても、どこか不均衡な感覚が拭えない」。即興ポートレートの挑戦を前に、私は今、この問いと向き合っています。慣れた紙か、新しい紙か。このジレンマは、「挑戦と安定のバランス」という普遍的なテーマに繋がります。歴史上のアーティストたちも追求した「準備された即興性」の中に、私の「流れ」と「大胆さ」を見出す探求の記録です。

Megumi Karasawa
7月5日読了時間: 6分
bottom of page